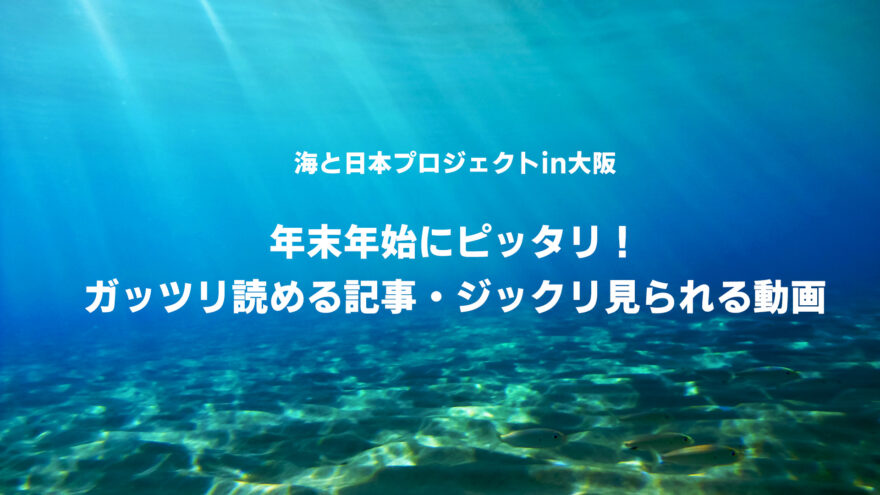うなぎの稚魚の密猟を防ぐ取り組み【ニュース紹介】

日本人にとって親しみの深いうなぎ。
とくに土用の丑の日として食べる事で滋養強壮や暑さ対策として知られています。
うなぎは完全養殖が難しく、稚魚を捕獲して育てる方式で養殖しています。
完全養殖とは、卵→稚魚→成魚→産卵→稚魚・・・という風に、ライフサイクルを人間の管理の元で全うさせる事です。
近年では近畿大学がマグロに次いでうなぎの完全養殖について発表を行いました。
そんなうなぎについて、現在多く採用されいてる稚魚を捕獲して育てる養殖について、稚魚の密漁が問題になっています。
うなぎの稚魚はレプトセファルスやシラスウナギと呼ばれており、2023年に改正漁業法の大幅な罰則強化が行われました。
うなぎに関しては13cm以下の稚魚の採捕が禁止され、最大で3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金の罰則が定められています。
稚魚の密漁や不正な流通を防ぐために、大手自動車部品メーカーのデンソーなどが愛知県にて、QRコードを使った流通経路の管理試験を開始しました。
これは自動車部品管理にも使われるQRコードを活用し、うなぎの稚魚の集荷や出荷の量や関連する事業者、そして取引日等の情報を入力し
流通経路を可視化することが目的です。
漁業者に負担の少ない管理方法として今年中に全国で運用することを目指しています。
宮崎県でもうなぎの稚魚の流通管理のためにQRコードを使用した試験運用が2024年12月から開始されており
2025年12月の本格運用に向け検証が行われています。
大阪府でもうなぎ漁は行われています。
淀川の加工では大きなうなぎがとれる事で有名です。
以前取材した、大阪市漁業協同組合の畑中さんは、うなぎ漁の現状分析と養殖魚と天然魚の共栄が必要だと語っています。
うなぎの種の保存、そしておいしい食材を環境負荷なく持続させることに繋がるといいですね。