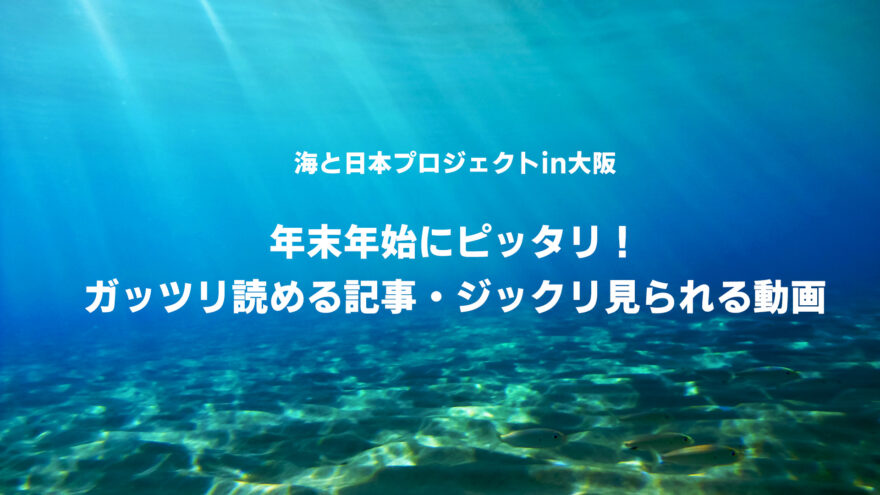お知らせ
2025.05.28
【ニュース紹介】ハゼも社会情報を利用している!

※画像はイメージです。
魚の中でも群れを作らない種類の魚であるアゴハゼ。単独で生活することで仲間と餌や餌場の争いをせずに生きることができます。
そんなアゴハゼですが北海道大学の研究チームによってアゴハゼの稚魚が同種の仲間から新たな餌と餌場の情報を得ていることがわかりました。
経験の乏しい稚魚は群れで生活する仲間から情報を得て過ごしていることがわかっていましたが、生まれてすぐ単独で生活をする魚が社会情報を利用するのはカレイ1種でしか確認されていませんでした。
今回は大きく系統の異なるスズキ目のアゴハゼで確認されたことから、摂食行動における社会情報の利用が様々な魚にも見られる可能性があることを示唆しているようです。
詳細はこちら「アゴハゼ稚魚は他個体の行動から摂餌課題を学ぶ」
摂食行動について海と日本プロジェクトin大阪でも取材を行いました。
取材したのは関西学院千里国際高等部の坂田さん。(2025年2月取材)
チヌの海とも呼ばれる大阪湾で、チヌが擬似餌(ルアー)を摂食するパターンについて研究を行いました。
もともと釣りが好きな坂田さん。なかでもチヌをメインとし好きが転じて研究をする事にしたそうです。
ルアーの色や質感、反射具合によって捕食する傾向に偏りがあることを発見されました。
魚は人間の顔を覚えることがなく自由に生きていると思われがちですが、同種でコミュニケーションをとりながら生きているんですね。